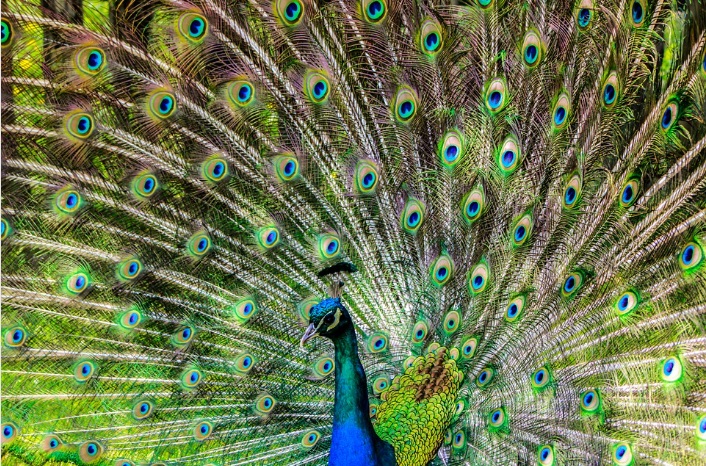オーガニックで肌荒れが悪化
オーガニックの表示があれば安全、と思って購入したのに、使ってみたらヒリついたり肌荒れが悪化した…という声をよく耳にします。パッケージやデザインだけで本物のオーガニックと信じてしまったのです。オーガニックという言葉は、心理的な安心感を与える効果があります。日本では、食品にはオーガニック規格が定められていますが、化粧品には明確な法的定義がありません。このため、オーガニックの表示に安心して購入して、使ってみたら肌荒れした…という事態が起きているのです。広告の文言やパッケージやデザインだけで本物のオーガニックと信じてしまったのです。
ほんの少しだけの植物エキス
オーガニック化粧品が注目を集める理由は、化学成分が肌に与える悪影響への懸念があります。敏感肌が多く発生しています。化学成分を一切使用しないオーガニックな天然成分であれば、肌トラブルを抑えてくれて、肌本来の美しさを引き出せるのです。植物のパワフルな栄養成分が、乾いた肌を潤し、エイジングケア効果をもたらしてくれます。ところが、「オーガニック」と表示されていても、実際には“ほんの少しだけ植物エキスを入れているだけ”で、大部分は合成成分の商品が多くあります。これが世の中に流通するオーガニック化粧品の大部分だと言ったら、あなたはきっと驚かれるでしょう。
ナチュラルさを謳っていても、成分表を見ると、実際にはケミカルだらけのものが大部分です。それでも「オーガニック化粧品」と表示できてしまうのです。これは違法ではありません。このため、巧みな言葉のプロモーションが横行し、オーガニックと表現されるのです。このことが、消費者に大きな誤解と混乱を生む原因になっています。
無添加は旧指定成分がないだけ
さらにややこしいのが、「ナチュラル」「自然派」「無添加」などの言葉です。これらの表示にも統一された基準はありません。このため、見た目や印象だけを言葉で訴えるマーケティングが行われています。例えば「無添加」とあっても、旧厚生省がアレルギーの可能性ありとして表示を義務付けていた102種類の旧指定成分を含まない、という意味で用いられることがほとんどです。それ以外にも肌に刺激を与える成分はたくさんあり、それが含まれているケースは少なくありません。こうした混乱のために、オーガニックと信じて、多くの人が「なぜ肌が荒れるの?」と困惑しているのです。
固定観念を捨てて中身を見る
まず、「オーガニック化粧品=肌に優しい」という固定観念をいったん手放すことが必要です。見た目や言葉の印象ではなく、その中身を知ることが大事だからです。どんな成分が、どのように製造され、どんなバランスで配合されているのか、そこまで目を向けてはじめて本当の「安心」が得られるのです。それこそが、自分の肌を守る第一歩です。正しい知識と視点もつことができれば、あなたの肌にとって、本当にやさしいものがなにか、選択ができるようになります。化粧品にとって本当に大切なのはイメージではなく”中身”なのです。
誠実な製品づくりのメーカーも
認証機関の認証を取得していなくても、オーガニック成分だけを使用している高品質なブランドは存在します。ただ、有害物質を極限まで排除した天然成分100%のオーガニック製品を消費者が探し当てるのは非常に至難です。なぜなら、こうした製品づくりをしているメーカーはごく一部に過ぎないからです。膨大な手間とコストがかかり、その努力は報われないことが多いためです。それでもあえて作られるこのような製品を”モア・オーガニック”と呼ぶことにします。その一例が、白樺樹液と国産ハーブを使った”ぷろろ化粧品”です。
伸び続けるも市場規模は小さい
オーガニックコスメを選ぶ際は、配合成分がご自分の肌に合うかどうかを確認することが大事です。オーガニック化粧品は、コロナ禍でも伸びが止まることなく、微増してきました。その後も毎年4%前後の伸びをつづけており、消費者の関心が増え続けていることを裏付けています。それは、合成界面活性剤や防腐剤、人工香料などを使わないオーガニックへと、消費者の関心が向かっていることを示すものです。ただ、化粧品市場全体から見れば、わずか5%程度に過ぎません。まだまだ小さい数字といえます。デンマーク、ドイツ、フランスのようなオーガニック先進国になりたいものです。
-
ヒト幹細胞化粧品を選ぶポイント
記事がありません